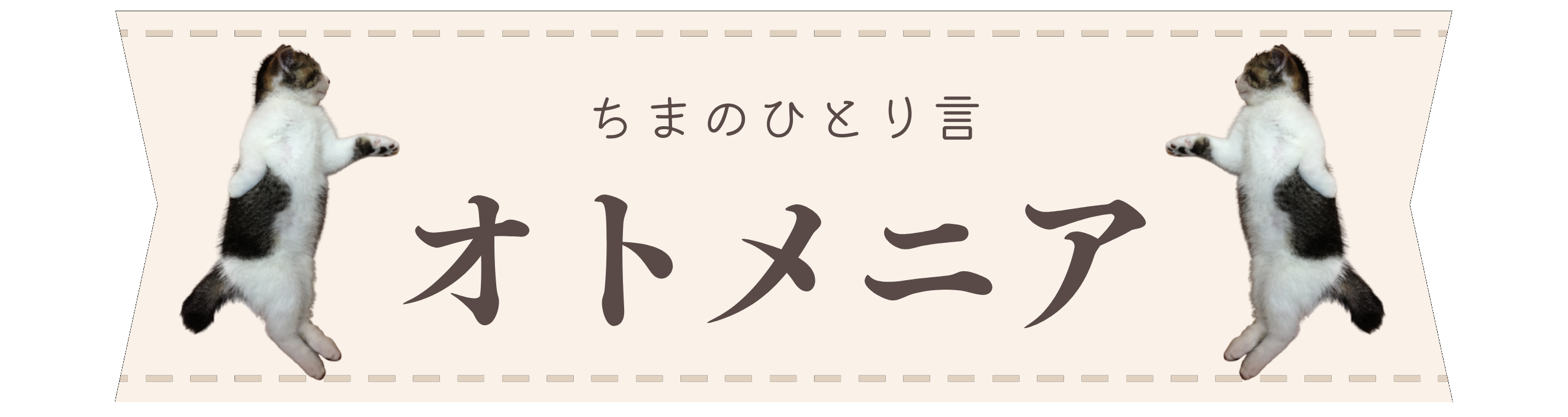ご挨拶
こんにちは、こんばんは、ちまです。
春の日差しが暖かく、干した布団を取り込むとそのままお昼寝をしたくなってしまいます。
今日お話しするのは、村上春樹さんの「風の歌を聴け」です。
あらすじ
1970年の夏、海辺の街に帰省した「僕」は、友人の「鼠」とビールを飲み、介抱した女の子と親しくなって、退屈な時を送る。2人それぞれの愛の屈託をさりげなく受けとめてやるうちに、<僕>の夏はものうく、ほろ苦く過ぎさっていく。青春の一片を乾いた軽快なタッチで捉えた出色のデビュー作。
ひとり言
村上春樹さんの「風の歌を聴け」を読みました。
村上春樹さんのデビュー作です。
1970年の夏、東京の大学生だった「僕」が海辺の街に帰省した19日間の話です。
冒頭、いきなり「完璧な文章などといったものは存在しない。 完璧な絶望が存在しないようにね。」という出だしで始まります。作家ならではの「文章」の捉え方だと思いました。
完璧の基準は人によって違います。
完璧を目指しながらも、心の片隅にこういう思いを持っていると救われる時があるのではないかと思いました。
物語が始まる前に、「絶版になったままのデレク・ハートフィールドの最初の一冊を僕が手に入れたのは中学3年生の夏休みであった。」そして、「僕は文章についての多くをハートフィールドに学んだ。」という話が出て来ます。このデレク・ハートフィールドという作家は、村上氏が創作した架空の作家です。この作家の生涯だけで、一冊の小説が書けそうです。村上氏の創造力の凄さを感じました。自分で創作した作家から文章についての多くのことを学ぶのですから。
1970年の夏、僕は「鼠」と呼ばれる友人とジェイズ・バーでビールを飲みながら日々を過ごします。鼠は女性のことで悩みを抱えていますが、悩みを僕に打ち明けようとしません。
僕は僕で、ジェイズバーで酔い潰れた女性を介抱して、やがて付き合うようになります。
鼠は僕の友人という設定で描かれていますが、読み進めて行くうちに、ふともう一人の僕ではないかと思えるようになってきました。
東京へ帰る日、僕は別れの挨拶をするため、「ジェイズ・バー」へ立ち寄ります。
ジェイは、「あんたが居なくなると寂しいよ。鼠もきっと寂しがる。」と名残りを惜しみます。こうした淡々とした日常の中で日々は流れて行きます。
「あらゆるものから何かを学び取ろうとする姿勢を持ち続ける限り、年老いることはそれほどの苦痛ではない。」
僕は20歳を過ぎた頃からずっと、そういった生き方を取ろうと努めます。そうした生き方をする僕に対して鼠は言います。
「みんないつかは死ぬ。でもね、それまでに50年は生きなきゃならんし、いろんなことを考えながら50年生きるのは、はっきり言って何も考えずに5千年生きるよりずっと疲れる。」
一見違う生き方のように思えますが、根底には似た思いがあるのだと感じました。
物語の中に、「時は、余りにも早く流れる。」「あらゆるものは通り過ぎる。誰にもそれを捉えることはできない。僕たちはそんな風にして生きている。」という文章が出てきます。
青春時代ならではの、切なさや儚さを感じました。
29歳になった僕は結婚し、東京で暮らしています。30歳になった鼠はまだ小説を書き続けています。そして、鼠は、毎年クリスマスに幾つかの小説のコピーを僕に送るのです。
「昨日があるから今日があり、今日があるから明日がある。そういうふうに日々は過ぎてゆく。そうした日々の移り変わりを見失わないように、今その時その時を大切に生きていきたい。風が奏でる歌を聴くことが出来たら、そこに自分の人生の何かが見えてくるのかもしれない 。」
読み終えた後、そんな風に感じた一冊でした。
今日が幸せな一日でありますように。