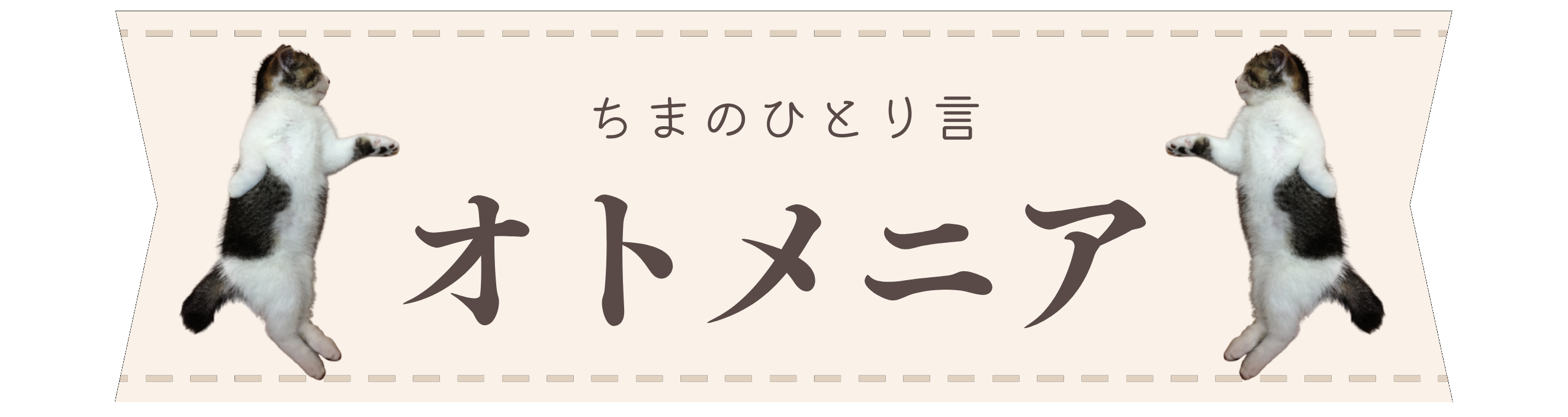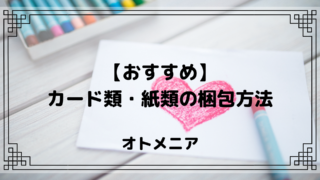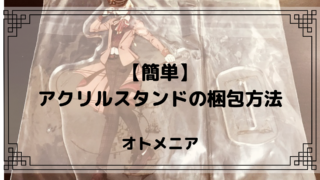ご挨拶
こんにちは、こんばんは、ちまです。
今さっき録ったデータがすべて消えてしまいました…。録り直しは中々辛いです(^^;)
今日お話しするのは、中村 理聖さんの「砂漠の青がとける夜」です。
あらすじ
瀬野美月は、東京で雑誌編集の仕事をしていましたが、姉が経営するカフェを手伝うため、仕事を辞め不倫を精算して京都に移り住みます。
そして美月は、カフェの常連客の中学一年生の準君と出会います。平日の夕方にコーヒーを注文し、どこか不安定さを感じさせる彼は、美月に、自分は他人とは異なる世界が見えるということを打ち明けます。繊細な情景描写と美しい文章が際立つ静かな感動作です。
ひとり言
中村 理聖さんの「砂漠の青がとける夜」を読みました。
瀬野美月は、京都で姉の菜々子が経営している喫茶店で働いています。元々は両親が経営していた喫茶店ですが、父が急死し、母も叔母のいるオーストラリアへ行ってしまったため、長女の菜々子が受け継いだのです。
美月は半年前まで東京の出版社で、飲食店の記事がメインの雑誌編集の仕事をし、既婚者の男性と恋愛をしていました。そうした中、菜々子から、フロアの接客女性が辞めたので、カフェの仕事を手伝ってくれないかという話があり、悩んだ末、勤めていた会社を辞め不倫関係にあった男性とも別れ、京都に来たのです。別れた男性からは、頻繁に「愛してる」というメールが届くようになっていました。
カフェのお客の中に、閉店間際の夕方、 カフェに1人でやって来て、一杯450円のコーヒーをオーダーする中学1年生の結城 準君がいました。彼の母親は京大で日本文学を教えていて、父親は京都市役所で働いています。両親は準君のことに無関心のようですが、父親が準君のいるカフェにいきなり迎えに来たり、月に一度家族で食事に行ったり、準君も母親の働いている姿を見たがったり、と不思議な親子関係です。そして両親の夫婦関係も、一見すると醒めているようですが、離婚という文字は浮かんできません。母親中心の不思議な家族関係です。
ある日、美月は偶然、菜々子の中学校時代の同級生だった織田聡史と出会います。彼は世界中を旅して、今は小学校の先生をしています。中学生の頃、織田と菜々子は世界地図を広げて世界一周計画を立てたりしていましたが、その後二人は別々の道を歩んでいました。菜々子は20代の頃、京大生との間に子を宿して、流産した経験があり、流産したのは自分の責任だと自分を責めて、京大生とは別れることになります。美月も菜々子も過去の恋愛経験を今もなお引き摺っています。織田は週に1度位の割合でカフェを訪れ、その後も二人は、つかず離れずの関係が続いています。奈々子の流産に対する自責の念とそのことを気遣う織田の気持ちが、二人が一歩を踏み出す障害になっているのでしょうか。
準君には、人の声と重なって、本音が聞こえ、本人ですら気づかない思いが 色や形や雰囲気として見えるという特殊な感性があります。そのため、人の声と言葉がうるさく感じられ、生活にも支障をもたらしています。でも、美月の声は一つだと言います。そうした美月と話すことは、準君にとって気持ちが楽になり、心が癒されたのではないかと思いました。
美月と準君の関係から目が離せません。仕事を辞め不倫を精算した美月、言葉の嵐に苦しみ、両親に愛されたいと思いながらも怯えている準君。二人の心はお互いに求め合って寄り添ったのだと思いました。姉と弟とも違う、お互いにそれぞれの存在が必要であると感じられる関係だと思いました。
この物語には、準君だけが聞こえる言葉や感じられる雰囲気、そして美月が不倫相手と一緒に、その時の状況の空気を詰めたボトルなど、独特の世界が描かれています。感性が人の心に与える影響の大きさを感じました。それと共に、モロッコの砂漠の夜の静寂を表現した繊細な情景描写や人の内面が本当に美しく描写されていて、引き込まれて読み進めました。
物語は、「準君にしか聞こえない声が美月に還り、緑と青が夜の闇に降りてくる。夢の中の世界で、砂漠の夜の青が空から舞い降りてくる。そして、美月は心の底からこみあげる言葉が「愛してる」の群れであることを、その時感じた。」と結ばれています。
準君が両親に愛されていることを感じ、美月が新たな愛を感じる日が来るのも間近だと感じた物語の終わりでした。そして、菜々子も織田の愛を感じる日が早く来れば良いなと思いました。
美しい文章に引き込まれながら、読後、心地よい不思議な空気を感じた物語でした。
今日が幸せな一日でありますように。