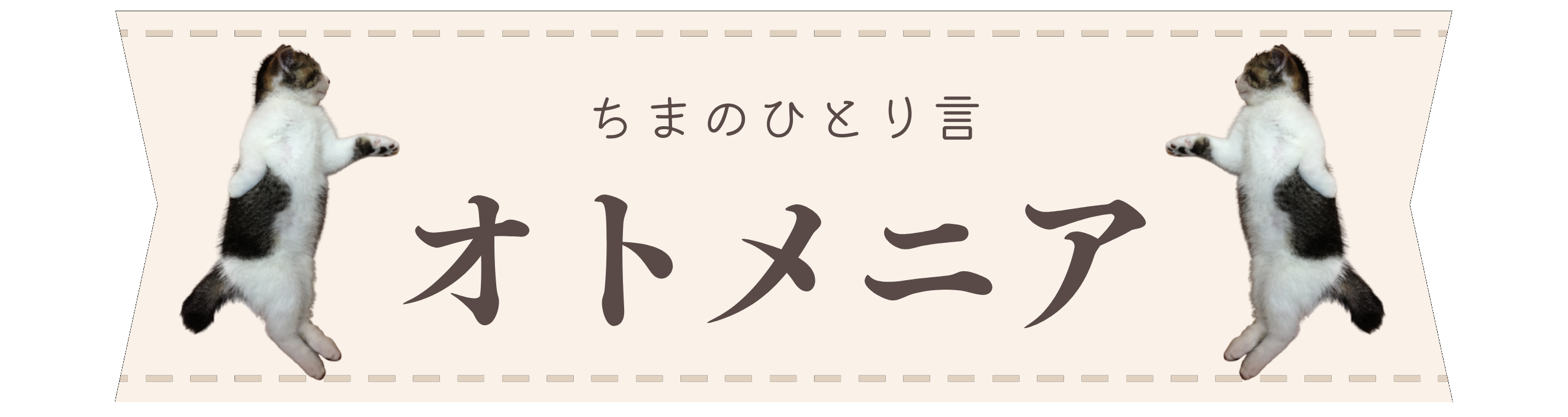ご挨拶
こんにちは、こんばんは、ちまです。
散歩をするようになって、今まで自分がどんなに運動不足だったのかを実感しました。
今日お話しするのは、藤原ていさんの「流れる星は生きている」です。
あらすじ
1945年の敗戦とともに満州(現、中国東北部)から、日本まで、3人の子をかかえ、はるかな道のりをたどった、著者の魂の記録。
ひとり言
藤原ていさんの「流れる星は生きている」を読みました。
この物語は、26歳のていさんが、6歳の正宏、3歳の正彦、生後1か月の咲子の3人の子どもを連れて、満州から引き揚げ、朝鮮半島の38度線を越え、故郷の長野県諏訪地方へ帰りつくまでの壮絶な過程が描かれたノンフィクションです。
ていは、高等女学校卒業後、気象庁に勤める藤原寛人(作家の新田次郎)と結婚し、夫の勤務先である満州へ渡ります。そして昭和二十年八月九日、ソ連の参戦により突然一人で三人の子供を抱えて満州から引き揚げることになります。
観象台の家族たちは「観象台疎開団」と自らを名づけ、汽車の中では集団行動を取り、北朝鮮北部の宣川(ソンチョン)で列車を降り、宣川農学校の校舎に収容されます。そして、8月15日の終戦を迎えます。この宣川で、一旦夫との再開を果たしますが、寛人は満州に戻り、その後非戦闘員であるにもかかわらずシベリア送りとなります。
事実に基づく汽車の中での描写も、宣川での1年に渡る集団生活の描写も、生死に関わる緊張の連続で、読みながら胸の痛みを感じるほどでした。
その後、日本人の集団は事実上解体し、ていは三人の幼子を連れて南下を始めます。38度線を越えればアメリカ軍がいると聞いて、眠る時間も惜しんで、死線をさまよいながら赤土の泥の中を歩き、徒歩で川の中を歩き続けます。言葉では到底表現出来ないような、生きるための壮絶な闘いです。そして、アメリカ軍のトラックに保護された時には、ていの足の裏は掘り返され、子どもの足の裏も化膿して酷い有り様でした。
何としても子供を守り抜くという、母親の本能と生きることを諦めない強靭な信念がていを支えていたのだと思いました。
その後貨車で釜山(プサン)まで運ばれ、引き揚げ船に乗り博多に着きますが、下船許可が下りず、船の中で死ぬ子どもたちもたくさんいました。
昭和21年(1946年)9月12日、ていと子供達はようやく博多に上陸し、汽車で故郷の長野県の上諏訪駅に到着し、やっと二人の兄と妹、そして両親と再会することができました。ていの子供達を守り夫と再会するという強靭な精神力が、再会へと導いたのだと思いました。
『私は両親に抱きかかえられるように支えられると、「これでいいんだ、もう死んでもいいんだ」「もうこれ以上は生きられない」霧の湖の中にがっくり頭を突っ込んで、深い所へ沈んでいった』という文章でこの小説は終わります。
精も根も尽き果て、子供3人と何とか生きて帰ることができた安堵感から出た言葉にハッとさせられ、そういう境地に陥るに至った壮絶な体験が改めて思い起こされました。
生死の淵に立たされた時の人間の振舞いの残酷さ、温かさそして、命の尊さがリアルに描かれ、読んでいて胸が苦しくなりました。けれども、そうした現実があったことに、私達は目を背けてはいけません。
ていさんは、あとがきで「最初は子供達が人生の岐路に立った時、また苦しみのどん底に落ちた時のための遺書として書いた。そしてその後本になった時、この本だけはたった一つの遺産として、彼らに生きる勇気を与えてくれるかもしれない」と書かれています。この『生きる勇気』という言葉は、現代の私達にとってもとても大事な言葉だと思いました。
戦争を知らない私達世代こそ、戦争によってこうした現実があったことを知っておく必要があり、私達は戦争の悲劇を二度と繰り返してはならないと強く感じました。
そのためにも、『流れる星は生きている』この本は次世代に渡って、ずっと読み継がれていかなければならない一冊だと思いました。
今日が幸せな一日でありますように。