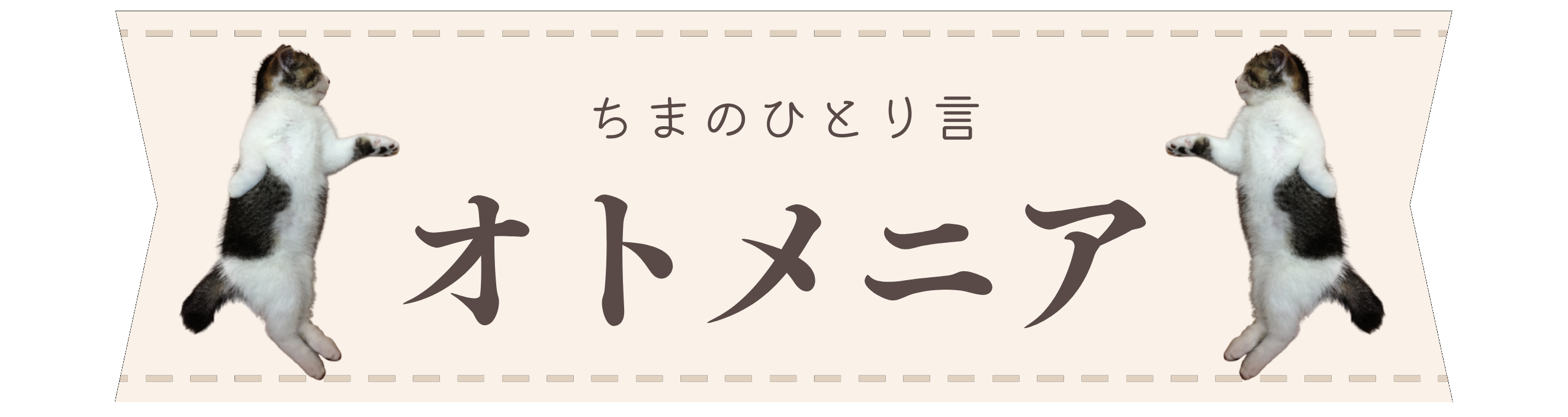ご挨拶
こんにちは、こんばんは、ちまです。
私の家は学校が近くにあるのですが、たまに管楽器の音が聞こえてきます。私も昔は吹奏楽部でトロンボーンを吹いていたので懐かしくなります。
今日お話しするのは、大崎 梢さんの「クローバーレイン」です。
あらすじ
大手出版社に勤める編集者の彰彦は、過去の人と言われている作家・家永の新作「シロツメクサの頃」を偶然目にします。その内容に感動した彰彦は、どうしても自分の手で本にしたいと思います。
それから本の出版に向けて、彰彦の奮闘が始まります。その思いは本に携わる人たちにも伝わり、多くの困難を乗り越えて、本は読者へと届けられます。本に携わる人たちの熱い想いに心を揺さぶられる物語です。
ひとり言
大崎 梢さんの「クローバーレイン」を読みました。
29歳の工藤彰彦は、大学卒業後、大手出版社「千石社」に就職して、順風満帆な編集者として意欲的に仕事に取り組んでいました。
そんなある日、彼は、ある作家のパーティーで、過去の作家と言われている家永嘉人と出会います。家永は酷く酔っ払っていたため、彰彦は、タクシーで家まで送ります。そして、家永を自宅まで送り届けた時、たまたま目にした新作の原稿を読みます。タイトルは、「シロツメクサの頃」。夜間中学を舞台にした物語です。その内容に感動した彰彦は、「どうしても自分の手で本にしたいので預からせてください。」と家永に頼みます。
翌日彰彦は、編集長に作品の素晴らしさを語り千石社から出版したい旨訴えますが、編集長は、「売り上げの見込めない作家の本は出せない。」と、取り上げてもらえませんでした。利益を優先する大手出版社の経営方針の苛酷さを感じました。
編集長の対応に落胆しながらも、それから「シロツメクサの頃」の出版を目指して、彰彦の奮闘が始まります。様々な困難な壁にぶつかりながら、書店員に人気のある千石社の敏腕営業社員の若王子、先輩女性編集者の赤崎、最初は取り上げようとしなかった編集長の矢野、ライバル会社の編集者の国木戸、家永の元担当編集者の鈴村、小説家の芝山など、多くの人に助けて貰いながら、出版に漕ぎ着けます。「シロツメクサの頃」に掲載されている詩を書いた家永の娘の冬美と彰彦の関係も興味深く、読み進めました。冬美がこの詩を書いた背景を知ると、この詩を書いた時の冬美の辛かった思いと優しさを感じました。
これまで売れっ子作家の作品を手掛けるなど、編集者として問題なく過ごしていた彼が、「シロツメクサの頃」の出版のために悪戦苦闘している姿は、この本の出版を冷めた目で見ていた周囲の心を次第に変化させ、やがて協力してやろうという思いに変わっていきます。読み始めた頃は嫌な奴と思っていた人が、読み進める内にどんどん好印象な人に変わっていきました。彰彦も自分の驕りや力不足を痛感し、周りの人に感謝しながら助けて貰います。一生懸命さは人の心を動かす力があるのだと、改めて感じました。
彰彦には、この本を読んで貰いたいと思う人がいました。祖父が不倫をしていた時の子どもの尚樹です。彰彦にとっては叔父にあたる尚樹ですが、歳の離れた兄のような存在で、本の魅力を教えたくれた人でした。最後の「シロツメクサの頃」を読んだ尚樹のメッセージには、心を揺さぶられました。『心配する相手がいるのは、それだけで幸せなのかもしれない。冬枯れの地面の下で、クローバーは春の訪れを待っている』。娘の心臓病と闘いながらも、疎遠になっている彰彦のことをずっと気にかけ心配している尚樹の優しさを感じるメッセージです。ずっと尚樹のことを気にかけていた彰彦にとっても、尚樹の存在は、幸せなことなのだと思いました。疎遠になっていても、お互いに気にかけている人がいることは、日々生きていく上で幸せなことなのですね。
彰彦は「シロツメクサの頃」を出版に漕ぎ着けることによって、編集者として大きく成長したと思いました。作品を生み出す作家の苦悩や出版に携わる編集者の想い、出版社の経営方針、出版に向けての装丁、出版後の営業に携わる人など、本に携わる数多くの人の労力や想いがあって、一つの小説が本になり読者の手に渡ることを再認識しました。改めて本が今まで以上に大切なものに思えました。
彰彦の奮闘で「シロツメクサの頃」が埋もれることなく読者の元へ届けられ、本好きの私は本当に嬉しく思いました。名作が埋もれることなく、私たち読者の元へ届くことを切に願います。
今日が幸せな一日でありますように。